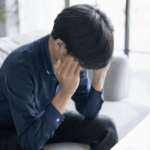交通事故で慰謝料がもらえない?原因と対処法を徹底解説
「交通事故の被害者になったのに、思ったより慰謝料が少ない」「加害者との示談で損をしてしまうのでは…?」。
実は、交通事故の慰謝料は手続きの方法や通院の仕方次第で大きく変わります。
この記事では、慰謝料がもらえない・減額される主なケースと、その防止策をわかりやすく解説します。
1. 慰謝料がもらえない主なケースと原因
交通事故で慰謝料が十分にもらえないケースは、以下のような理由によって発生します。
- 弁護士基準ではなく、任意保険基準で示談してしまった
- 通院期間が短い、または途中で中断した
- 整骨院のみの通院で医師の診断がない
- 後遺障害等級の認定が適切に行われていない
- 示談交渉で増額要素を主張できなかった
- 過失割合を不当に高く設定された
- 損益相殺や素因減額で不当に減額された
- 時効により損害賠償請求権が消滅した
どれも「手続きを知らなかった」ことが原因で損してしまう典型例です。
次章では、実際にどのような状況で減額・支払い拒否が起きやすいのかを詳しく見ていきましょう。
2. 入通院慰謝料がもらえないケースと対処法
① 弁護士基準で計算していない
保険会社が提示する金額は、ほとんどが「任意保険基準」で計算されたものです。
弁護士が用いる「弁護士基準(裁判基準)」と比べると、2〜3倍の差がつくこともあります。
損を防ぐには、弁護士基準での再計算が必須です。
② 治療を中断した・通院頻度が低い
通院期間や頻度が少ないと、保険会社は「治療の必要性が低い」と判断します。
最低でも月に1回以上、できれば週1〜2回のペースで通院を続けましょう。
また、医師の指示を守らないと治療の相当性を否定される可能性があります。
③ 通院先が整骨院や接骨院のみ
整骨院や接骨院での施術は、医師の診断・紹介がない限り、通院実績として認められにくい傾向にあります。
必ず病院で医師の診断を受けてから整骨院に通うようにしましょう。
3. 後遺障害慰謝料がもらえないケースと解決策
① 等級が適切に認定されていない
後遺障害等級が1〜14級で決まる金額は大きく、1等級違うだけで数百万円変わります。
適正な認定を受けるには、「被害者請求」で必要書類を自ら準備し、医師の後遺障害診断書の内容を弁護士と確認することが大切です。
② 弁護士基準での請求をしていない
後遺障害等級が認定されても、任意保険基準のままでは慰謝料が低く抑えられます。
弁護士基準の算定表を用いて正確な金額を請求することで、増額が見込めます。
| 後遺障害等級 | 弁護士基準の慰謝料目安 |
|---|---|
| 1級 | 約2,800万円 |
| 5級 | 約1,400万円 |
| 9級 | 約690万円 |
| 14級 | 約110万円 |
4. その他のケース(過失・損益・時効)
- 過失割合: 保険会社が一方的に高く設定してくる場合あり。判例タイムズ等を基に反論を。
- 損益相殺: 保険金や年金が誤って差し引かれていないか確認。
- 素因減額: 既往症や体質を理由に減額された場合は医学的証拠で反論。
- 時効: 人身事故は5年、物損は3年で時効。早期の相談が重要。
ご自身やご家族の自動車保険・火災保険・クレジットカードにも付帯している場合があります。
交通事故の慰謝料・示談金でお悩みの方へ
示談金の中に慰謝料が含まれていることを正しく理解し、損しないための判断を。
交通事故専門の無料相談なら「ジコまど」がサポートいたします。
5. 弁護士に依頼するメリット
- 弁護士基準での慰謝料計算が可能(最大2〜3倍に増額)
- 示談交渉・書類提出を全て任せられる
- 過失割合や相殺の不当な主張を防げる
- 精神的負担の軽減・時効管理も万全
6. まとめ
交通事故の慰謝料でもっとも重要なのは、正しい基準で金額を計算すること。
弁護士基準で請求すれば、示談金が大幅に変わる可能性があります。
「今の提示額が妥当かわからない」と感じたら、まずは無料相談で確認してみましょう。