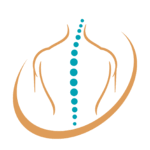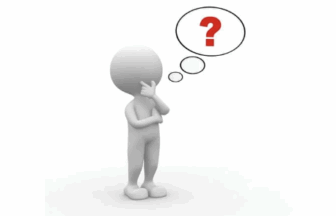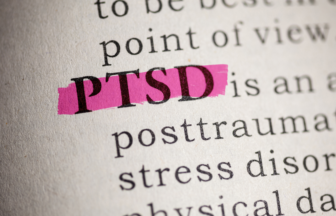交通事故の後遺障害、認定を受けるための準備とは
交通事故の直後は、痛み・不安・手続きの多さで「何から始めればいいの?」と戸惑いやすい時期です。後遺障害の認定(後遺障害等級認定)を見据えるなら、実は早期からの医療機関受診と、整骨院への計画的な通院がとても重要です。この記事では、専門的な視点をやさしくかみ砕きつつ、整骨院に通院する重要性を中心に、認定までに押さえるべき準備、失敗しやすいポイント、そして「ジコまど」に相談した場合の流れを、事例を交えながら丁寧にご案内します。
目次
- 後遺障害認定の基礎知識:なぜ「準備」が大切?
- 整骨院に通院する重要性と、医科(整形外科)との役割分担
- 認定で重視される「記録」のつくり方(受診頻度・空白・症状の一貫性)
- ジコまどに相談した場合の解決までの流れ
- 事例紹介:年齢・症状・状況と、準備が生んだ成果
- いますぐできるセルフチェック(無料)
- よくある質問(整骨院・認定・保険の実務)
- 参考リンク・統計データ
- まとめ:「ジコまどでは交通事故に関する悩みをなくしたい」
1. 後遺障害認定の基礎知識:なぜ「準備」が大切?

後遺障害認定とは、治療を続けても完全には回復しない症状(痛み・しびれ・可動域制限・神経症状など)が残ったときに、その状態・影響の程度を客観的に評価する制度です。認定の有無・等級は、補償額や今後の生活再建に大きく関わるため、適切な医療や記録の積み重ねが欠かせません。
認定で見られる主な要素
- 医学的所見の有無(診断名、画像所見、徒手検査、神経学的所見 など)
- 症状の一貫性・持続性(事故直後からの訴えと通院記録の整合性)
- 治療経過(受診頻度、改善・悪化の推移、リハビリや施術の内容)
- 日常生活・就労への影響(家事・仕事・学業の支障、復職状況)
ここで大切なのが、事故直後から「医科(整形外科)」と「整骨院」を適切に併用し、抜けのない記録を重ねること。後述しますが、整骨院の施術録や痛みの推移メモは、医師の診断書と相まって症状の連続性・具体性を補強します。
2. 整骨院に通院する重要性と、医科(整形外科)との役割分担
「整骨院に通うメリットは?」「病院だけではだめ?」というご質問をよくいただきます。結論からお伝えすると、医科と整骨院は役割が異なり、併用することで機能が補完されます。
医科(整形外科)の主な役割
- 診断・医学的評価:画像検査(X線・MRI等)、診断名の確定、症状固定の判断
- 投薬・処方:痛み止め、湿布、ブロック注射など
- 診断書・後遺障害診断書の作成
整骨院の主な役割
- やさしい徒手療法・物理療法で、痛みの軽減・機能回復を目指す
- 日々の体調変化を丁寧に把握し、施術録として経時的に記録(痛みの部位、強さ、可動域、日常生活動作の支障など)
- 自宅でできるセルフケアや姿勢・生活動作の指導で再発予防
認定の場面では、「事故直後から現在までの症状のつながり」が客観資料で示せるかが鍵です。整形外科の診断書に加えて、整骨院の連続的な施術記録があると、症状の持続性・一貫性を補う材料となります。空白期間(何週間も受診がないなど)が長いと、「本当に症状が続いているのか?」と疑念を招くリスクがあるため、無理のない頻度で継続通院することをおすすめします。
最新の対処法や注意点を発信中。事故後ケアのヒントを日々更新しています。
3. 認定で重視される「記録」のつくり方(受診頻度・空白・症状の一貫性)
後遺障害は「いま痛い」だけでは足りず、その痛みが事故と医学的に結びついていることの説明が重要です。以下は、実務上とても大切なポイントです。
(1)初期受診のタイミング
事故当日〜数日以内に医科(整形外科)での初診が理想です。初期受診が遅れると、事故との関連が弱まる懸念があります。整骨院の受診は、医科で診断を受けつつ並行して行うと、記録が充実します。
(2)受診頻度と空白期間
痛みが続いているのに通院が空くと、「症状は軽快していたのでは?」と評価されやすくなります。ご自身の体調に合わせて、週1〜2回など現実的な頻度で継続しましょう。体調が良い日も、どの動作で痛みが出るかを具体的に記録してください。
(3)症状の表現は「具体的に」
- 痛みの部位:首の右側、肩甲骨周囲、腰の左側 など
- 痛みの質:ズキズキ、重だるい、しびれ感 など
- 痛みの強さ:NRS(0〜10)で毎回記録
- 生活への影響:洗濯物を干す・パソコン作業・長時間の運転など具体的な動作
これらは整骨院の施術録や、ご自身の症状日誌(メモアプリでもOK)として残せます。一貫性のある記録は、後遺障害診断書の作成時にも医師の判断を助けます。
📞 ジコまど相談窓口: https://jikomado.com/
4. ジコまどに相談した場合の解決までの流れ

ジコまどは、事故後の不安や疑問を解消するための無料相談窓口です。保険交渉は行いませんが、状況に応じて医療機関・整骨院・弁護士・行政書士・車両修理などの専門家と連携し、「あなたに今必要な一歩」を一緒に設計します。
ご相談〜解決イメージ(3ステップ)
- ヒアリング(無料):事故日/受診歴/痛みの内容/お困りごとを整理。
▶ LINEで質問テンプレをお送りします。 - 受診と記録の設計:整形外科の受診タイミングや、整骨院での通院計画・症状日誌の書き方を提案。
- 専門家との連携:必要に応じ弁護士等をご紹介(交渉は弁護士へ)。認定を見据え、資料の抜け・空白が出ないよう並走します。
このプロセスにより、「何をいつまでに、どう整えるか」が明確になり、認定を見据えた準備がブレずに進みます。
最短30秒で無料相談スタート。事故後の不安を、今すぐ質問に変えましょう。
ジコまどが「できること/できないこと」
- できること:状況整理、受診先や整骨院のご紹介、記録づくりの支援、専門家ネットワークへの橋渡し、車両修理の相談 など
- できないこと:保険会社との交渉(示談・賠償の交渉は行いません)。交渉が必要な場合は弁護士へおつなぎします。
5. 事例紹介:年齢・症状・状況と、準備が生んだ成果
事例A:32歳・女性/事務職/自転車で追突され首肩痛(むち打ち)
状況:下校途中の車と接触し転倒。翌日から首〜肩の痛み、頭痛、デスクワークで悪化。
行動:事故翌日に整形外科を受診し診断名確定。その後、整骨院に週2回通院し、NRS(痛みスケール)・可動域・日常生活の支障を毎回記録。
結果:症状固定時に医師が後遺障害診断書を作成。整形外科の経過+整骨院の連続記録が揃ったことで、症状の持続性と具体性を示す資料が充実。弁護士とも連携し、適切な評価につながりました(交渉は弁護士が担当)。
学び:初動の速さと、「医科×整骨院」併用の一貫した記録がカギ。
事例B:17歳・男子高校生/バイク転倒で腰痛・脚のしびれ
状況:雨天でスリップ転倒。若年で痛みを我慢しがちで、部活へ復帰を急いでいた。
行動:家族が伴走し、整形外科の画像検査→整骨院のリハビリを併用。学校生活での支障(座位保持・授業中の痛み)を教員の協力も得て記録。
結果:症状の波があっても、欠席日数・保健室利用・部活制限などの客観的事実が積み上がり、資料の説得力が向上。
学び:未成年は周囲の支援で客観的記録を増やすことができる。空白期間を作らない通院が重要。
事例C:68歳・男性/追突事故後の頚部痛+手のしびれ/ドライバー
状況:日常的に運転が必要。痛みで睡眠が浅く、仕事にも影響。
行動:整形外科で神経学的検査を受け、整骨院で可動域改善・姿勢指導。運転時間・休憩回数、家事の分担変化を家族とともに日誌化。
結果:高齢者特有の既存の変性所見が疑われるケースでも、事故前後の生活比較と通院記録で変化の実像が示せた。
学び:既往や加齢変化があっても、事故後に具体的に何が困っているかを客観的に積み上げることが大切。
※注意:上記事例は説明用のモデルケースです。結果は個別事情・医学的所見によって異なります。保険交渉はジコまどでは行いません(必要に応じて弁護士をご紹介)。
6. いますぐできるセルフチェック(無料)
- 事故翌日までに医科(整形外科)を受診しましたか?
- 整骨院へは週1〜2回など現実的な頻度で継続できていますか?
- NRS(0〜10)で痛みを毎回メモしていますか?
- 家事・仕事・学業で困った具体的動作を書き出せていますか?
- 空白期間(通院ゼロ期間)が長く空いていませんか?
- 症状固定の見込み時期や、後遺障害診断書の準備ポイントを主治医と共有できていますか?
一つでも迷いがあれば、無料で並走します。公式LINEへお気軽にどうぞ。
迷ったら、すぐ相談。状況整理から始めましょう。
7. よくある質問(整骨院・認定・保険の実務)
Q1. 整骨院だけに通っていても大丈夫?
医科(整形外科)での診断・経過観察は必須級です。整骨院は機能回復・痛みの緩和に役立ちますが、認定では医師の診断書が土台になります。医科×整骨院の併用を基本方針にしましょう。
Q2. どのくらいの頻度で通えば良い?
体調に合わせつつ、空白期間を作らないことが大切です。週1〜2回など持続可能な頻度で、痛みの推移と生活への影響を毎回記録しましょう。
Q3. 仕事や家事で通院が難しい…どうすれば?
通いやすい時間帯の整骨院をご紹介できます。自宅ケアの指導を得て、在宅での工夫(就寝環境・デスク環境・休憩ルール)も合わせて最適化しましょう。
Q4. ジコまどは保険会社と交渉してくれる?
いいえ、保険交渉は行いません。交渉が必要な場合は、弁護士をご紹介し、準備資料の整理に注力します。
Q5. 何から始めればいいか分かりません…
まずは無料ヒアリングで現状を整理し、受診・記録・専門家連携のロードマップを一緒に作ります。今からでも間に合います。
8. 参考リンク・統計データ
- ジコまど(公式サイト):https://jikomado.com/
- 福岡県警・交通事故統計:https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/toukei/trafficaccident.html
- 警察庁・交通事故統計:https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/index.html
- 国土交通省・自賠責保険制度(交通事故被害者保護):https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html
- 厚生労働省 e-ヘルスネット(健康情報):https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/
9. まとめ:「ジコまどでは交通事故に関する悩みをなくしたい」
後遺障害の認定を見据えるなら、事故直後からの正しい受診と、整骨院での継続的なケア、そして一貫した記録づくりが成功の鍵です。医科×整骨院の併用は、症状の持続性・具体性を証明するうえでとても有効で、生活再建への最短ルートになります。
ジコまどは保険交渉を行いません。その代わり、あなたが迷わず前へ進めるよう、受診・記録・専門家連携の設計に全力で伴走します。ひとりで抱え込まないでください。あなたの痛みや不安に、寄り添い、整理し、解決に向けて具体的に動く。それが私たちの役目です。
「ジコまどでは交通事故に関する悩みをなくしたい」——その思いで、今日もご相談をお待ちしています。
📞 ジコまど相談窓口:https://jikomado.com/
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な判断は医師・弁護士等の専門家にご相談ください。