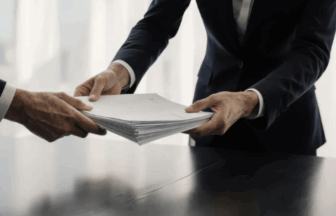慰謝料はいくらもらえる?計算方法をやさしく解説
交通事故のあと、「慰謝料はいくらになるの?」「整骨院に通った方がいいの?」と不安に感じる方は多いものです。この記事では、慰謝料の考え方と計算の基本をやさしく整理しつつ、なぜ整骨院に通院することが重要なのかを、専門的な視点とわかりやすい言葉でお伝えします。福岡を中心に全国対応の交通事故の無料相談窓口「ジコまど」へのスムーズな相談導線もご用意しました。まずは落ち着いて情報を整え、一緒に最適な一歩を踏み出しましょう。
目次
- 慰謝料の基本:基準と考え方
- やさしい計算の流れ(傷害・通院時)
- 整骨院に通院する重要性と“記録”の力
- 整形外科と整骨院の役割の違い・併用のコツ
- ジコまどに相談してから解決までの流れ
- 具体事例:年齢・症状・状況・成果
- よくある失敗と回避策
- よくある質問(Q&A)
- 関連リンク
- 最後に:ジコまどの思い
1. 慰謝料の基本:基準と考え方

交通事故の慰謝料には大きく分けて、(1)傷害(けが)に対する慰謝料、(2)後遺障害に対する慰謝料、(3)死亡慰謝料といった枠組みがあります。ここでは、多くの方が直面する傷害(通院期間中)の考え方を中心に解説します。
また、慰謝料の金額を考える際には、一般に以下の3つの基準が用いられます。
- 自賠責基準:最も基本的な公的基準。通院・治療の「日数」「期間」「実績」が重視されます。
- 任意保険基準:保険会社ごとの内部基準。概念的には自賠責と裁判基準の中間イメージ。
- 弁護士(裁判)基準:裁判例等をもとにした基準。状況により金額水準が異なります。
どの基準が適用されるか、どのように主張・立証していくかで、最終的な慰謝料の見立てが変わります。ここでカギになるのが「医療記録」と「通院の一貫性」です。単に痛みを我慢したり自己判断で湿布だけに頼るよりも、医療機関や整骨院で症状を“客観的に”記録していくことが、結果的にご自身を守ることにつながります。
2. やさしい計算の流れ(傷害・通院時)
傷害の慰謝料(通院期間中)では、一般に「通院の実日数」や「総治療期間」から基礎日数を算定し、所定の単価を掛け合わせて概算します。実務では次のような考え方がよく使われます。
- 総治療期間(初診日から治療終了日までの日数)を把握する。
- 通院の実日数(実際に通った日数)を整理する。
- 基礎日数の決め方:
・「実日数×2」または「総治療期間の一定割合」のうち、より低い方を採用する考え方が一般的です。
・具体の単価や割合は毎年度の運用や基準で変動し得るため、最新の水準を確認することが大切です。 - 単価×基礎日数=慰謝料の目安(傷害分)。
ポイントは、「通院の実績」と「継続性」が正しく反映されること。ここで整骨院に通う意義が生きてきます。体の不調を放置せず、早期に受診し、症状と施術の経過を丁寧に記録していくことで、基礎日数の認定や症状の一貫性の評価に資する可能性が高まります。
📞 ジコまど相談窓口: https://jikomado.com/
3. 整骨院に通院する重要性と“記録”の力
3-1. 痛みの「見える化」と継続ケア
むち打ち・打撲・腰痛など、画像検査で異常が映りにくい症状は、日々の痛みの変化や機能制限を経過で示すことが大切です。整骨院では、可動域評価・疼痛部位の推移・日常生活動作(ADL)の改善度などを丁寧に記録し、施術計画(頻度・目的・注意点)を立てます。これらの記録は、症状の一貫性・合理性の裏づけになり得ます。
3-2. 「中断リスク」を避ける
通院が途切れると、「もう治ったのでは?」と捉えられるリスクが高まります。忙しい時期こそ、週1〜2回でも継続し、セルフケア(自宅でのアイシング・軽いストレッチ・睡眠衛生)の記録も残しましょう。連携する整形外科での定期診察と併用できれば、より強い一貫性が確保できます。
3-3. 早期受診の意味
初期対応が遅れると、原因関係の立証が難しくなる場合があります。事故から早期(理想は当日〜数日以内)に受診し、診断書の取得・施術記録の作成を進めることが重要です。
4. 整形外科と整骨院の役割の違い・併用のコツ
整形外科は診断・医学的評価(画像検査、投薬等)、整骨院は機能回復を目的とした手技・物理療法・運動指導が中心とイメージしてください。どちらか一方ではなく「併用」が現実的で、月1回以上は整形外科で診察・証拠化、その間を整骨院で丁寧にケアしていく流れが理想です。
- 整形外科:診断書、投薬、必要に応じてリハビリ指示
- 整骨院:疼痛緩和、可動域改善、日常生活への復帰支援、セルフケア指導
この併走の軌跡が、回復と記録の両輪になります。
5. ジコまどに相談してから解決までの流れ

ジコまどは保険会社との交渉(示談交渉)を行いません。交渉は弁護士の専門領域であり、必要に応じて提携・連携する専門家をご紹介します。ジコまどは、被害者の方の状況整理・通院動線の設計・専門家連携に特化した無料相談窓口です。
- 公式LINEで相談(無料・全国対応)。
- 15〜30分のヒアリング:事故状況、症状、生活・仕事の制約、既往歴をやさしく確認。
- 通院計画の設計:整形外科&整骨院の併用プラン、頻度、セルフケア指導、記録の取り方。
- 必要に応じて専門家へ接続:弁護士・行政書士・修理工場など。交渉自体は弁護士が担当します。
- 経過フォロー:痛みの変化・通院回数・生活上の困りごとをフォローし、次の一手を一緒に検討。
6. 具体事例:年齢・症状・状況・成果
事例A:28歳・女性(福岡市)/追突事故・頸部痛・頭痛
- 状況:信号待ちで追突。翌朝から首肩の強い張りと頭痛。最初は「数日で治る」と放置。
- 対応:ジコまどに相談後、即日で整形外科受診→診断書取得。以後、整骨院に週2回、整形外科は月1回の併用へ。
- 記録:痛みスケール(0〜10)、可動域、睡眠状態、仕事中の支障を日誌化。
- 成果:3か月でADL(家事・デスクワーク)が改善。通院実績と症状推移の一貫性が整理でき、適切な基礎日数の評価につながった。本人も「我慢せず通ったことが自分を守った」と実感。
事例B:42歳・男性(久留米市)/自転車事故・腰部痛・坐骨神経様症状
- 状況:夕方の交差点で接触。自転車で転倒、腰部痛が強く、翌日から歩行時痛。
- 対応:整形外科で画像検査→安静指示。整骨院で疼痛緩和と骨盤周囲の安定化トレーニングを開始。
- 記録:歩行時間、階段の昇降レベル、就労時間、痛みのピーク時間帯を可視化。
- 成果:6週間で痛みが半減。通院中断ゼロで、実日数の積み上げと回復過程の合理性が明確に。仕事復帰がスムーズになり、生活クオリティが向上。
事例C:35歳・女性(北九州市)/側面衝突・肩関節周囲炎様の可動域制限
- 状況:側面からの衝撃。肩の挙上で激痛。洗濯物を干す・髪を結ぶ動作が困難。
- 対応:整形外科で診断→整骨院で段階的な可動域訓練と生活動作の指導。夜間痛に対するセルフケアも併用。
- 記録:可動域角度(屈曲・外転)を数値化、家事時間の増減をログ化。
- 成果:2か月で生活動作の8割が改善。日常生活への具体的影響が記録で分かるため、症状の真実味・継続性が伝わりやすくなった。
7. よくある失敗と回避策
- 受診が遅い:事故直後の受診が遅れると、原因関係の説明が難しくなります。早期受診+記録開始を。
- 通院が途切れる:仕事・家事の都合で空白が生じたら、理由を記録し、次回以降の計画をすぐ再開。
- 整骨院のみで完結:整形外科の診断書・定期診察は可能な限り確保しましょう。
- 症状の伝え漏れ:痛みの質(ズキズキ・重だるい等)、時間帯、生活への影響をメモ。次回の施術・診察で共有。
8. よくある質問(Q&A)
Q1. 通院が多い方が必ず有利ですか?
量よりも一貫した必要性が大切です。症状と施術内容、生活上の改善が記録でつながっていることが評価の土台になります。
Q2. 仕事で頻繁に通えません。どうしたら?
頻度を週1〜2回に調整し、自宅でのセルフケア(ストレッチ、睡眠、姿勢)も記録しましょう。整形外科の定期診察は可能な範囲で継続してください。
Q3. 慰謝料の具体的な単価は?
単価や細かな算定ルールは年度・運用で変動する場合があります。最新の水準を必ず確認しましょう。迷ったら、まずは無料で状況整理をご一緒します。
Q4. ジコまどは示談交渉をしてくれますか?
いいえ。ジコまどは保険会社との交渉(示談交渉)を行いません。交渉が必要なときは、弁護士などの専門家をご紹介します。私たちは、相談・通院動線設計・記録づくり・専門家連携に特化しています。
9. 関連リンク
10. 最後に:ジコまどの思い
事故は、ある日突然に日常を揺さぶります。体の痛みだけでなく、仕事や家事、家族の時間、将来への不安まで影響します。だからこそ私たちは、「整骨院への通院」というやさしい選択で、あなたの回復と「記録づくり」を支え、必要な専門家へ最短でつなぐことに力を注いでいます。ジコまどでは交通事故に関する悩みをなくしたい。その思いを胸に、今日も一人ひとりに寄り添います。迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
📞 ジコまど相談窓口: https://jikomado.com/