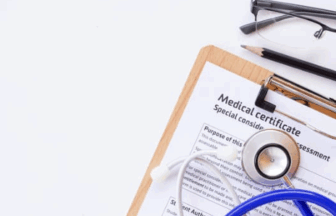交通事故の「休業補償」と「休業損害」を最短で整理迷ったらこの順で
交通事故で仕事を休むと、労災の休業補償と自動車保険の休業損害という2本立ての制度が絡みます。名称が似ていても、対象・計算・提出先が違うため、順番を誤ると受け取れる額やスピードに影響します。本ガイドでは、実務で迷いやすいポイントを入れ替えて、まず何を出し、どこへ連絡し、いくら見込めるかを一気に把握できるよう構成しました。

1. まず整理:休業補償と休業損害の違い
| 項目 | 休業補償(労災) | 休業損害(自動車保険) |
|---|---|---|
| 対象 | 業務災害・通勤災害 | 交通事故全般(相手の任意/自賠責、または自分の特約) |
| 要件 | 療養で労務不能+賃金不払い | 事故で収入減が生じたこと |
| 計算の軸 | 給付基礎日額×80%(60%給付+20%特別) | 基礎収入×休業日数(基準により異なる) |
| 提出先 | 労働基準監督署 | 保険会社(相手・自分) |
| 併用 | 重複分は支給調整。特別支給金などは単独受給可 | 労災と重複分は調整 |
最短ルート:通勤・業務上→まず労災。業務外→自動車保険で休業損害。迷えば両ルートの要件を同時に満たす形で記録・書類準備を。
2. 労災の休業補償|対象・要件・通勤災害の範囲
- 要件3つ:①業務・通勤に起因する負傷/疾病の療養中 ②そのため労務不能 ③賃金不払い。
- 通勤災害の「通勤」:住居⇄就業場所、単身赴任先⇄帰省先、就業場所⇄他就業場所の移動を合理的経路・方法で。
- 勤務中の事故は業務災害として取り扱い。
3. 支給開始・終了の考え方(待期3日/症状固定)
- 開始:休業4日目から(最初の3日は待期・会社負担が原則)。
- 終了:治癒(含:症状固定)または労務可能化。症状固定後は障害(補償)給付の対象へ。
- 重篤で長期なら傷病補償年金へ移行の可能性あり。
4. 労災の金額計算:給付基礎日額→80%の内訳
4-1 給付基礎日額
原則は「平均賃金」=事故直前3か月の賃金総額÷歴日数。1円未満は切り上げ。
最低保証:給付基礎日額が低すぎる場合の下限は4,090円(令和6年8月1日適用)。計算値が下回れば自動で底上げ。
4-2 休業補償給付の算式
- 支給額=給付基礎日額×80%(内訳:60%=休業補償給付、20%=休業特別支給金)
- 端数処理:1円未満は切り捨て(支給計算時)。
例:基礎日額6,522円 → 60%=3,913円/20%=1,304円 → 合計5,217円/日
5. 労災の書類・申請フロー・支給方式
必要書類
- 様式第8号 または 様式第16号(休業(補償)給付支給請求書)
- 労働保険番号、請求者情報 ほか(監督署の指示に沿う)
手順
- 労基署へ請求書提出
- 労基署の調査(ヒアリング・資料確認)
- 支給/不支給の決定
- 支給決定なら指定口座へ振込
請求は原則本人。負傷が重い場合、会社が補助・代行するケースもあります。
支給方式
- 一括/分割の選択可。長期休業は1か月ごとの請求が基本。
6. 有給・他給付(傷病手当金/失業)との関係
- 有給取得日は対象外:賃金支払いがあるため二重受給は不可。
- 傷病手当金と併用不可:制度目的が重複。
- 失業給付と同時不可:労災は労務不能、失業は就労可能が前提のため要件が相反。
7. 事業場が未加入でも受けられる?
労災保険は労働者1人でも雇用すれば原則加入義務。未加入でも、被災労働者は労災適用の対象です(自ら労基署で手続)。未加入を把握した段階で労基署に相談すれば、事業主へ加入指導が入ることがあります。
8. 打切りの条件・不服申立(審査請求)の道筋
- 打切りになり得る場面:①治癒 ②症状固定 ③受給開始1年6か月経過時の要件移行 等
- 治癒に至らず1年6か月超でも、所定の届出で継続可のケースあり。
- 不服:決定を知った翌日から3か月以内に労災保険審査官へ審査請求 → さらに不服なら労働保険審査会(2か月以内)。行政訴訟も選択肢。
9. 税務/賞与の扱い・特別支給金とボーナス
- 非課税:労基法8章に基づく給付(休業補償など)は原則非課税。
- 休業手当(会社都合)は給与所得で課税。
- 賞与:就業規則・労使協定に依存。査定期間に休業があれば不支給や減額の可能性も。
- 特別支給金と賞与:本体給付にはボーナスは反映されないが、特別支給金の一部に影響しうる運用あり。
10. 休業損害(自動車保険):基準・職業別の算定
10-1 基準の違い
- 自賠責基準:原則日額6,100円×休業日数(証明で最大1万9,000円/日)
- 任意保険基準:社内基準。おおむね自賠責同等〜やや上
- 裁判(弁護士)基準:もっとも高額になりやすい。
基本式=基礎収入×休業日数(給与者は「事故前3か月の給与÷稼働日数」等)
10-2 職業別の代表算式
| 区分 | 自賠責 | 任意保険(例) | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 給与所得者 | 6,100円×日数(要証明で上限引上げ可) | 6,100円×日数 or 直近3か月給与÷90×日数 | 直近3か月給与÷稼働日数×日数 |
| 自営業 | 同上(証明で〜1万9,000円) | 社内基準 | (前年申告所得+固定費)÷365×日数 |
| 専業/兼業主婦(夫) | 6,100円×日数 | 社内基準 | 専業:女性全年齢平均賃金÷365×日数/兼業:高い方の基準 |
ポイント:弁護士基準は稼働日数で割るため、1日あたりが上振れしやすい。収入証明・就労制限の医学的裏付けが鍵。
11. 休業損害の必要書類・期間・よくある不支給
必要書類(一例)
- 休業損害証明書(勤務先作成)
- 源泉徴収票・賃金台帳・雇用契約書等(給与者)
- 確定申告控・請求書・通帳写し等(自営業)
- 家族全員の住民票(家事従事者の実態証明)
期間
原則:事故日〜治療終了(症状固定)まで。具体の可否は医師の客観的判断が前提。
よくある不支給
- 就労可能と判断:診断書の記載から労務制限が読み取れない。
- 収入証明不足:源泉徴収票や確定申告が整っていない。
→ 不足しても自賠責の日額6,100円は請求余地あり。
12. 家族の付き添い費/過失割合の影響
- 付添費:入院・通院・在宅・通学の付き添いが必要な程度なら請求可(医師所見の裏付けを)。
- 過失:自賠責は被害者過失7割以上で重過失減額(2〜5割)。その場合は労災の休業補償を優先検討(過失の影響を受けない)。
13. 弁護士に頼むと何が変わる?
- 金額面:任意基準→裁判(弁護士)基準への乗せ替え交渉。医師意見書の手配で就労制限の立証を強化。
- 手続面:必要書類の特定・取り寄せ支援、期限管理、保険会社とのやり取りの一本化。
- 不服申立:労災の不支給・打切りに対する審査請求/再審査請求、裁判対応まで一気通貫。
【免責】本稿は一般的な情報提供です。実際の可否・金額・提出先・様式・期限は地域や個別事情で異なります。最新の運用は所轄機関・保険会社・就業規則をご確認ください。