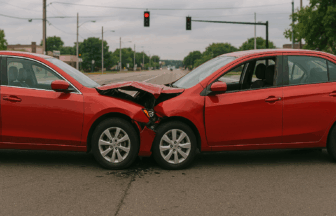交通事故の診断書で損をしないために保存版
診断書は、事故後の補償・保険・法的手続のスタートラインです。作成の一手間で、慰謝料や後遺障害の認定、休業損害の評価まで結果が変わります。本ガイドは、被害者が迷いなく動ける実務フローに組み替え、つまずきやすい場面の対処と、専門家へ相談するタイミングまで一気通貫で解説します。
1. 診断書が「補償の出発点」になる理由
診断書は、医学的に事故との因果関係・傷病名・初診日・治療見込みを示す公式記録。警察の人身切替え、保険会社とのやり取り、後遺障害等級の審査、裁判に至るまで、すべての根拠文書として機能します。内容の粗さや欠落は、そのまま補償の取りこぼしに直結します。
2. 取得の実務:どこで・いくらで・どのくらいで手に入る?
2-1 どこで/どう頼む?
- 受診先:整形外科・救急外来・脳神経外科など症状に合う科。
- 依頼時に伝える:提出先(警察/保険/職場)・事故日・初診日・主症状・就労影響。
2-2 費用の目安と負担者
- 一般的に2,000〜10,000円程度(医療機関・内容により異なる)。
- 原則は一旦立替え。損害賠償で回収可(領収書必須)。保険会社が直接支払う運用の地域もあるため要確認。
2-3 作成スピード
- 簡易:即日〜翌日/詳細:1〜3週間が目安。
- 緊急時は簡易→後日詳細の二段構えに。
3. 記載ズレで損しない:目的別の書き方・必須項目
3-1 初期診断書(警察・社内報告向け)
- 必須:事故日・初診日・傷病名・部位・全治(見込み)・通院/入院の要否。
- 注意:全治見込みは支払期間の叩き台にされがち。経過で更新前提の認識を共有。
3-2 経過・詳細診断書(保険・職場向け)
- 必須:症状推移/処置・投薬・リハ/他覚所見(MRI・X線等)/就労・日常生活への影響/今後の方針。
- 提出先の様式指示がある場合は様式に合わせて依頼。
3-3 後遺障害診断書(症状固定後)
- 必須:症状固定日・後遺症の詳細・検査所見・ADL影響・既往歴の影響・予後。
- ここが等級と慰謝料・逸失利益を左右。交通事故に詳しい医師/弁護士と準備を。
3-4 精神科・心療内科の診断書(うつ・PTSD等)
- 因果関係の明示、症状の頻度と重症度、就労・生活影響、治療内容、評価尺度などを具体に。
- 精神症状は立証が難しいため、専門医+継続通院の記録が鍵。

4. 提出先・提出期限・遅延リスクと最適タイミング
| 提出先 | 主目的 | タイミング | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 警察 | 人身切替え・事故記録 | なるべく早く(一般に10日以内目安) | 遅れるほど因果関係が疑われやすい。 |
| 保険会社(相手・自分) | 治療費・慰謝料・休業損害 | 事故報告後すぐ/更新は経過に応じ継続 | 最新の診断書で随時アップデート。 |
| 職場 | 就労配慮・傷病手当等 | 会社規程に従う | 労災該当時は手続き別途。 |
遅延リスク:提出が遅いと、「事故由来のケガではない」と判断され、補償が縮む/打切りの口実になります。
5. 修正・追加・再発行:現場で起きがちな「あるある」の直し方
- 記載漏れ:作成医に具体的箇所を指摘→訂正印または再作成。
- 症状追加・悪化:追加診断書を発行し、変化点・撮像所見を明記。
- 紛失:再発行(費用は自己負担が一般的)。
6. 特殊ケース:整骨院・労災・医師が書いてくれない時
6-1 整骨院/接骨院の証明は「診断書」ではない
柔道整復師の施術証明は医学的診断書と同等扱いになりません。保険・警察・後遺障害の評価軸は医師の診断が前提。整骨院を併用する場合も、整形外科主治医の許可と経過共有を。
6-2 労災が絡む場合
- 通勤・業務中=労災ルート。労基署手続(初期診断書含む)と第三者行為届を忘れずに。
- 指定医療機関なら窓口負担なし。
6-3 医師が書いてくれない?
| よくある理由 | 対処 |
|---|---|
| 症状固定前なので様子見 | 医師指示に従い通院継続→時期を見て再依頼 |
| 後遺障害は否定的 | 自覚症状を具体化・画像検査の必要性を相談 |
| 整骨院のみ通院 | 医療機関へ切替え、医師の経過管理下に |
| 転院直後で情報不足 | 前医情報を提供、一定期間通院後に再依頼 |
| 紛争関与を嫌う | 医師変更/弁護士からの依頼書添付で依頼 |
7. 診断書が補償額に与える影響と後遺障害の要点
- 治療費・入通院慰謝料:診断書の期間・通院頻度・処置内容が計算の基礎。
- 休業損害:就労制限の有無・期間の記載で説得力が変わる。
- 後遺障害:症状固定日/他覚所見/ADL記載の精度が等級と金額を左右。
- 精神症状:専門医の詳細な診断書と継続通院記録が鍵。弁護士介入で裁判基準へ近づけやすい。
8. 加害者側の確認ポイント:疑問がある時の正しい進め方
- 保険会社経由で内容説明を受け、事故状況と整合するか確認。
- 不一致は医療アドバイザーの所見やセカンドオピニオンを保険会社経由で依頼。
- 安易な「虚偽」主張は禁物。証跡(ドラレコ等)で冷静に検討。必要時は弁護士に。
- 自分の怪我も正直に申告。記録の隠蔽は長期的に不利。
9. 弁護士に頼むと何が変わる?相談導線と費用感
9-1 メリット
- 診断書の質を底上げ:不足項目の洗い出し・追加検査依頼・医師への依頼文作成。
- 賠償交渉の土台を裁判基準へ:提示額の見直し、増額交渉のロジック構築。
- 手続負担の軽減:保険会社対応の窓口一本化、期限管理。
9-2 相談タイミング
- ベストは事故直後〜通院初期。遅くとも症状固定前/後遺障害申請前。
9-3 費用感(一般例)
- 相談料:30分5,000円前後(無料枠あり)
- 着手金:0〜50万円(交通事故は無料プランの事務所も)
- 成功報酬:経済的利益の一定割合+定額(例:10%+20万円 など)
- 弁護士費用特約:保険で実質自己負担ゼロも(契約により上限あり)
10. よくある質問(Q&A)
Q1. 物損で届けた後でも人身に切り替えられますか?
A. はい。医師の診断書を警察に提出して切替え申請を。早いほど有利です。
Q2. 整骨院だけ通っていました。保険は出ますか?
A. 医師の診断・経過管理が前提です。整形外科へ切替え、以後併用を。
Q3. 診断書の全治見込みが短すぎます。
A. 経過で最新診断書に更新し再提出を。初期値は暫定と理解しましょう。
Q4. 保険会社の提示額が低い気がします。
A. 自賠責/任意基準の可能性。弁護士基準での見直しを弁護士へ。
無料で流れを整えたい方へ(相談先のご案内)
まずは「いま必要な診断書」と「提出順序」を一緒に整理しましょう。
症状・通院状況に合わせて、初診→診断書→警察(人身切替)→保険会社への提出まで、あなたに合うステップを短時間で設計します。
※保険会社との直接交渉は行いません。交渉が必要な場合は、連携弁護士をご案内します。
【免責】本記事は一般的情報です。地域や提出先により運用が異なる場合があります。具体的な可否・様式・期限は各機関へご確認ください。