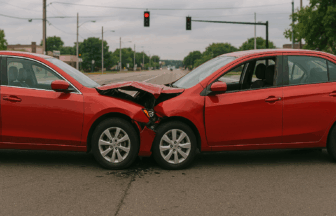後遺障害とは?等級認定・慰謝料相場・申請方法・異議申立てまで|交通事故相談窓口ガイド
交通事故相談窓口の現場でよく相談される「後遺症」と「後遺障害」の違い、等級認定の流れ、慰謝料の算定基準、必要書類、異議申立て、被害者/加害者それぞれの実務ポイントを、窓口対応でそのまま使える順序でまとめました。
まずは無料で状況整理から
1. 後遺症と後遺障害の違い(定義/要件)
後遺症:治療を継続しても完治せず、機能障害・神経症状などが残る状態。
後遺障害:次の全要件を満たし、自賠責の等級表に該当すると認定されるもの。
- 後遺症が残っている
- 医学的に事故との因果関係が証明されている
- 労働能力の低下・喪失が認められる
- 自賠責の定める基準(等級)に該当する
要点:「後遺症がある=後遺障害の慰謝料が出る」ではありません。等級認定が必須です。

2. 等級認定の概要(1~14級の考え方・部位別の要点)
自賠責(自動車損害賠償保障法施行令)の別表第1・第2に基づき、症状固定後の医学的資料から1~14級のいずれかに当てはめます。
| 部位/症状 | 代表的な認定ポイント | 代表的な等級例 |
|---|---|---|
| 目(視力/視野/運動/調節) | 視力低下の数値・視野検査・複視・調節障害の所見 | 1~3級、4級、6級、8~10級、11~13級 など |
| 耳(聴力/耳鳴り等) | オージオ等の検査値、会話理解距離 | 4級、6級、7級、9~11級、12・14級 など |
| 鼻・口(咀嚼/言語/嗅覚/味覚) | 機能障害の有無と程度、歯科補綴本数 | 1・3・4・6・9・10・12級 等 |
| 神経系(むちうち/高次脳/RSD等) | 画像/神経学的検査、認知機能評価 | 別表1-1級/別表2-2級、3・5・7・9・12・14級 |
| 上肢/下肢(欠損/可動域/変形/短縮) | 関節可動域、偽関節、短縮差、画像 | 1・2・4・5級、7~14級 |
| 外貌・体幹・長管骨 | 醜状の範囲、脊柱変形、長管骨変形 | 6・7・8・9・11・12・14級 等 |
| 内臓・生殖器 | 機能低下・人工肛門等の医療措置 | 1~11級、13級 等 |
3. 慰謝料の算定基準と相場(自賠責/任意/弁護士)
3-1. 三つの基準
- 自賠責基準:国の最低限補償。等級ごとに定額目安。
- 任意保険基準:各社内部基準(非公開)。自賠責よりやや高いことが多い。
- 弁護士(裁判)基準:判例水準。一般に最も高い。
3-2. 目安金額の一例(令和2年4月1日以降・要点)
| 等級 | 自賠責の目安 | 弁護士基準の目安 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,150万円(介護要は1,650万円) | 2,800万円 |
| 2級 | 998万円(介護要は1,203万円) | 2,370万円 |
| 3~7級 | 861~419万円 | 1,990~1,000万円 |
| 8~14級 | 331~32万円 | 830~110万円 |
4. 申請方法(事前認定/被害者請求)と必要書類
4-1. 申請ルート
- 事前認定:加害者側の任意保険会社が手続き。手間は少ないが提出資料の主導権は相手側。
- 被害者請求:被害者自身が自賠責へ直接請求。手間は増えるが、提出書類を精査しやすい。
4-2. 必要書類(要点)
- 後遺障害診断書(医師作成・検査所見/経過/症状固定日)
- 診療報酬明細・診断書、レントゲン/MRI/CT、神経学的検査所見
- 交通事故証明書、事故状況報告、印鑑証明 など
5. 認定されなかった時の異議申立て(方法・注意点)
- 損害保険料率算出機構へ再審査請求
- 自賠責・共済紛争処理機構での審査
- 訴訟(裁判所の判断を求める)
6. 検査・医証の集め方(画像・神経学的検査)
- 画像:レントゲン/MRI/CT(必要部位を網羅、再撮影を含む)
- 神経学的検査:徒手筋力・腱反射・知覚・スパーリング等の客観所見
- 高次脳:神経心理検査(WAIS/WMS等)・復職可否の評価
重要:症状固定前に必要検査が未了だと、等級判断が不利になります。固定は医師と十分協議のうえで。
7. 時効・リスク・示談後に症状が出た場合
- 時効:被害者請求は症状固定から原則3年以内(事案により異なるため要確認)。
- リスク:認定待ちの間は示談が止まる、訴訟で低い等級判断のリスク等。
- 示談後の発症:原則追加請求不可。ただし予見困難な後遺症は例外的に請求が認められる裁判例あり(個別判断)。
8. 相談先(ADR/医療/弁護士)と依頼タイミング
- ADR:日本損害保険協会「そんぽADRセンター」など(苦情・紛争解決)
- 医療機関:症状固定の可否・追加検査・診断書の充実
- 弁護士:申請書面の戦略設計、不足医証の補正、示談/訴訟の代理
タイミング:重症例や後遺が疑われる場合は早期に。固定直前~申請前が特に有効。
一人で抱えず、初動で「順序」と「資料」を整えましょう(無料)
9. 【加害者向け】認定後に必要な賠償の範囲と保険の使い方
9-1. 賠償項目の基本
- 治療費・文書費・通院交通費(必要かつ相当な範囲)
- 休業損害(現実の収入減/主婦主夫含む家事労働の評価)
- 傷害慰謝料・後遺障害慰謝料(3基準)
- 逸失利益(基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数)
9-2. 保険の実務
- 任意保険加入あり:示談代行・各種費目の支払実務を保険会社が対応。
- 未加入:自賠責超過分は加害者が自己負担となる可能性。
ポイント:被害者側の請求が過大と感じる場合でも、法的根拠と医証に基づき冷静に協議。弁護士関与で適正化が図れます。
10. よくある質問(窓口での説明テンプレ)
Q1. 保険会社の提示額は妥当?
任意保険基準は非公開で、一般に自賠責寄りの水準。弁護士基準との乖離が大きい場合、専門家で比較検討を。
Q2. 後遺障害の交渉は自分でできる?
可能ですが、相手が基準を上げる義務はなく、医学的整理と判例水準の主張立証が必要。弁護士関与で通りやすくなります。
Q3. 整骨院だけで通うと不利?
整形外科主導が前提です。画像・診断書・経過記録が不足すると認定/金額で不利になりやすいです。
Q4. 打ち切りと言われたら?
まず医師に必要性の意見書/診断書を依頼し、医証を添付して継続交渉。必要に応じて自費継続+後日請求も検討(領収書保管)。
参考リンク・根拠(確認用)
- e-Gov法令検索:道路交通法
- e-Gov法令検索:自動車損害賠償保障法施行令(等級表)
- 国土交通省:自賠責保険の支払基準(金額改定の有無は最新情報を確認)
- 日弁連交通事故センター東京支部:損害賠償額算定基準(通称:赤い本)
- 紛争処理:日本損害保険協会(そんぽADRセンター)
- 交通事故相談窓口:ジコまど(無料相談)(保険交渉は非対応)
【ご注意】本記事は窓口対応用の一般情報です。最新の金額・運用は改定される場合があります。最終判断は公的資料・医療機関・弁護士等の最新情報でご確認ください。