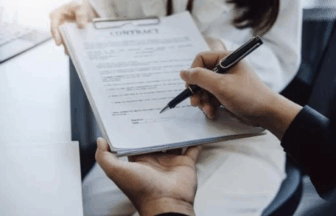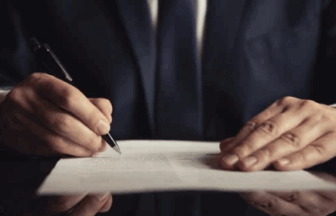交通事故と労災保険業務災害/通勤災害とメリット
1. 労災保険を使える2つのケース
① 業務災害(仕事中の事故)
- 例:トラック・タクシーなど業務運転中の事故、営業職の外回り中の事故、現場間の移動時の事故 等
② 通勤災害(通勤途上の事故)
- 例:出勤・退勤の往復中の交通事故、合理的経路上の寄り道を除く移動中の事故 等
覚えておく 労災は「仕事中」だけでなく通勤中も対象になり得ます。まずは該当性を検討しましょう。
2. 労災保険を使うメリット
メリット① 相手保険会社からの「治療費打ち切り」がない
任意保険での一括対応では、相手保険会社の判断で治療費の打ち切りが行われがちです。
労災では政府の保険から給付されるため、一方的な打ち切り圧力を受けにくく、必要な治療の継続がしやすくなります。
メリット② 後遺障害認定のチャンスが増える/通りやすさ
後遺障害は労災(労基署ルート)と自賠責で審査主体が異なります。
実務感覚として、症状・資料が適切であれば労災の方が比較的認定に至ることがある印象もあります。
また、制度が別のため審査機会が二重化できる点も利点です。
メリット③ 治療費が過失相殺の対象にならない(費目拘束)
労災給付された治療費は、加害者への請求で過失相殺の控除対象に算入されません。
そのため、同じ事故でも最終手取り(被害者側の受領額)が増える可能性があります。
3. 労災を使わない場合との比較(数値例)
前提:総損害100万円(うち治療費50万円)。被害者側過失30%(=過失相殺0.7)。
| 比較項目 | 労災を使わない(任意保険一括) | 労災を使う |
|---|---|---|
| 損害算定の母集団 | 100万円(治療費50万を含む) | 50万円(治療費は労災給付で除外) |
| 過失相殺 | 100万 × 0.7 = 70万円 | 50万 × 0.7 = 35万円 |
| 既払い調整 | 任意保険が先払いした治療費50万円を控除 → 残20万円 | 治療費は労災給付のため控除なし → 35万円 |
| 被害者の最終受領見込み | 20万円 | 35万円 |
同じ事故でも、労災を使うだけで最終手取りが大きく変わるケースがあります。
業務災害・通勤災害に該当しそうなら、早期に労災申請ルートを検討しましょう。
4. 実務の注意点
- 該当性の精査: 通勤経路の逸脱・中断があると通勤災害の認定に影響します。
- 医証の整備: 症状経過・必要性・就労影響は診療録と診断書で丁寧に記録。
- 二重取りの回避: 労災給付と加害者賠償の整合(求償・控除の扱い)を前提に設計。
- 保険会社対応: 任意保険からの「打ち切り」示唆が出たら、弁護士相談のタイミングです。
任意保険の枠での話し合いだけで進めると、過失相殺・既払い控除の影響で不利な着地になりがちです。
労災の活用は交渉全体のゲームプラン(後遺障害認定・賠償配分)に直結します。
5. まとめ
- 労災は業務災害と通勤災害の2ルート。まずは該当性を確認。
- メリットは打ち切りリスクの低さ/後遺障害の審査機会/過失相殺の影響緩和。
- 数値比較からも、労災の活用で最終受領額が増えることがある。
- 判断に迷ったら早期に専門家へ。