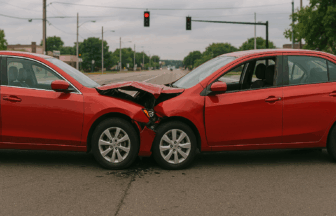交通事故問題解決の流れ
交通事故は多くの方にとって初めての出来事。身体の痛み・通院・仕事や家族の都合が重なる中で、賠償交渉まで一人で抱えるのは負担が大きいのが実情です。適正な賠償を受け取るには、事故直後からの一手がその後を左右します。本ガイドは、被害者・ご家族が迷わず動けるよう、時系列フローと実務の要点をまとめました。
以下は一般的解説です。事案により適切な対応は異なります。不安があれば早期に専門家へご相談ください。
全体フロー(俯瞰)
| 段階 | 目的 | 主なアクション |
|---|---|---|
| ① 事故直後(当日) | 生命の保護/二次災害防止/証拠の初期確保 | 119・110通報/安全確保/相手情報確認/現場記録/当日受診・診断書 |
| ② 初動数日 | 事実認定の土台形成 | 実況見分立会い/供述整合/ドラレコ保全/関係先連絡(自分の保険等) |
| ③ 治療期 | 症状固定までの医療と費用整理 | 通院計画/領収書・明細保存/就労・家事影響の記録/主治医との連携 |
| ④ 交渉準備 | 請求根拠の可視化 | 損害算定書作成/過失割合の検討/資料目録化/示談草案 |
| ⑤ 交渉・ADR | 適正額での合意 | 提示額の査定/反論書面/内容証明等で経緯化/ADR検討 |
| ⑥ 訴訟(必要時) | 争点の司法解決 | 立証計画/証人・意見書/和解or判決/履行確保 |
1.その日のうちにやるべきこと
(1) 警察への通報(110)
事故現場では必ず警察に通報し、事故の検分を受けましょう。交通事故証明書は保険手続・事実認定の基礎資料となります。軽微でも「内々で示談」は危険。後日の体調変化や事故態様の主張が食い違い、紛争化しがちです。
道路交通法72条は、救護・危険防止・報告を義務づけています。報告義務違反には罰則(119条)が予定されています。
(2) 情報の収集・記録
- 相手方の氏名・住所・連絡先・勤務先
- 車両番号・所有者/管理者(所有者が賠償責任を負う場合あり)
- 保険会社名・契約番号・連絡先
- 目撃者の連絡先、現場・損傷の写真(全景→中景→近景)
最低限、車両ナンバーを控える。ドラレコは上書き防止(電源断・SD退避)。
(3) 病院での受診
自覚症状が軽くても当日受診し、診断書を取得。治療費・交通費等の領収書は保管。健康保険は原則使用可能です。自費前提と言われた場合も、適用を求めることができます。
Q. どの病院でも良い? → A. 信頼できる医療機関でOK。ただし事故と無関係な治療・過度な遠距離通院は賠償対象外になり得ます。
2.そのあと早めにやるべきこと
(1) 捜査機関への協力(実況見分・供述)
人身事故では実況見分が実施され、実況見分調書が作成されます。接触位置・視認地点・停止位置等は過失判断の核心。立会い時に、記憶に沿わない点はその場で指摘しましょう。
当事者の供述は後の認定に強く影響します。曖昧な表現は避け、客観資料(写真・映像・痕跡)と整合的に説明を。
(2) 加害者・保険会社との連絡
自身の加入保険(人身傷害・弁護士特約等)へも早期連絡。加害者側任意保険とのやり取りは、診療経過・費目の明細化を意識して進めます。
Q. 加害者加入の保険会社に直接請求できる? → A. 強制保険(自賠責)は法で認められ、任意保険も約款で被害者請求の仕組みがあることが一般的です。
Q. 示談前でも支払いは受けられる? → A. 自賠責は可能。任意保険は原則示談・判決後ですが、内払が運用される場合もあります。
3.現場対応・医療・交渉で生じやすい問題点
- 現場状況の不一致:優先関係・信号・速度・視認の評価が割れる。
- 後遺障害の立証:症状固定時点・等級認定で金額が大きく変動。
- 因果関係の争い:治療内容・期間・費用の必要相当性。
- 示談書の不備:文言不明確で履行・再請求のトラブル。
提示額は根拠の開示(式・率・資料)を求め、安易に署名しないこと。
4.専門家ができること(実務支援)
- 診断書・医療記録の取得・照会、症状固定の助言、後遺障害申請の戦略設計。
- 実況見分調書・現場写真・ドラレコの解析、過失割合の評価。
- 損害算定書の作成(入通院慰謝料・休業損害・逸失利益・将来介護・雑費等)。
- 交渉・内容証明での経緯化、ADR/訴訟への移行判断と立証計画。
弁護士特約があれば自己負担ゼロ〜低額で依頼できることが多い領域です。
5.書類・証拠の整え方
| カテゴリ | 主な資料 | ポイント |
|---|---|---|
| 事故・現場 | 交通事故証明書/実況見分調書/現場・車両写真/ドラレコ | 全景→中景→近景の順で網羅。上書き防止と保管。 |
| 医療 | 診断書/診療明細/画像データ(CD)/紹介状 | 症状の推移・治療計画を時系列で整理。 |
| 損害 | 領収書(交通費・雑費・装具)/休業証明/給与・確定申告 | 費目ごとにファイル化。摘要欄に日付・内容・往復経路。 |
| その他 | 相手保険会社との往復書簡/電話記録/メール | 交渉経緯はタイムライン化し、論点の固定化を図る。 |
6.交渉・示談の進め方
- 損害算定書を提示(根拠式・率・資料を添付)。
- 相手提示額の内訳を開示要求。食い違いは論点別に切り出し。
- 合意案は文言精査(清算条項・履行期・遅延損害金・振込先)。
- 難航時はADR(紛セ・日弁連ADRなど)や訴訟へ選択。
示談成立前でも、自賠責の範囲での立替払・仮渡金等の制度活用を検討。
7.訴訟に進む場合の見取り図
訴訟は事実認定と法的評価の分業。準備書面で論点を明確化し、証人尋問・鑑定・意見書で立証を補強。和解の機会も複数回設けられます。
- 主な争点:過失割合/因果関係/症状固定時期/後遺障害等級/損益相殺。
- 期間の目安:地裁で概ね数ヶ月〜1年超(事案の複雑性・期日の密度で変動)。
- コスト・リスク:印紙・郵券・鑑定費用・弁護士費用/時間的負担。
訴訟前から証拠目録・時系列・論点表を整備しておくと、手続移行の負担が大幅に軽減します。
8.Q&A(よくある疑問)
Q. 整骨院・整体院の費用は賠償されますか?
A. 医学的必要性や医師の指示、症状改善の実態等が要件。一律に可否は決まりません。病院記録と整合を取ることが重要です。
Q. 自分にも過失があると言われています。
A. 過失相殺は総額に直結。視認・接触位置・速度・規制等の客観資料で丁寧に反証を。
Q. 提示額が妥当か判断できません。
A. 各費目(慰謝料・休業損害・逸失利益)の内訳・式・率を精査。第三者評価で増額余地を検討します。
9.チェックリスト(保存版)
- □ 当日受診・診断書取得・領収書保存。
- □ 現場写真(全景→中景→近景)・ドラレコ保全・目撃者連絡先。
- □ 実況見分に立会い、記載内容の確認。
- □ 自身の保険・弁護士特約へ連絡。
- □ 損害算定書のドラフト作成(根拠添付)。
- □ 提示額の内訳開示を要求し、差異は論点表に。
- □ 難航時のADR・訴訟ルートを早期に想定。
「迷い」を「手順」に。初動の一手から伴走します。
事故直後の判断・証拠の集め方・医療との連携・示談の進め方──やることは多いですが、手順化すれば前に進めます。状況を伺い、あなたの事案に最適化したフローを一緒に作ります。