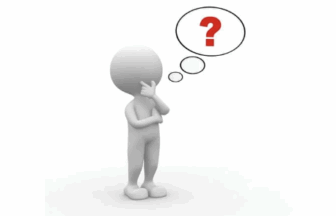交通事故の時効とは?2020年民法改正で変わった「3年と5年の壁」
1. 時効とは|請求しなければ“消える”権利
損害賠償請求権は、一定期間行使しないと「時効」によって消滅します。
時効が完成すると、加害者側は支払わなくても良いという抗弁が可能になり、被害者は正当な請求をしても認められません。
つまり、「事故から何年経ったか」は法的に非常に重い意味を持ちます。
「落ち着いたら請求しよう」と後回しにすると、取り返しのつかない結果を招くこともあります。
2. 改正前と改正後の比較|“人的損害”が延長された
| 区分 | 改正前(~2020年3月) | 改正後(2020年4月~) | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 人的損害(身体・生命) | 3年 | 5年 | 治療費・慰謝料・後遺障害・死亡事故など |
| 物的損害(車・建物等) | 3年 | 3年(変更なし) | 修理費・物損・器物破損など |
改正民法(第724条の2)では、「人の生命または身体を害する不法行為」に限り、時効が3年→5年へ延長。
精神的損害(慰謝料)も人的損害に含まれます。
3. 適用の分かれ目|2020年4月1日をまたぐ事故はどうなる?
ポイントは「時効が完成していたかどうか」です。
- 2020年4月1日時点ですでに時効3年が満了していた事故 → 旧法が適用
- 満了していなかった事故 → 新しい民法が適用され、5年ルールに延長
つまり2018年以降の事故で、2020年4月までに3年が経っていない場合は改正民法が適用されます。
被害者にとっては救済の範囲が広がった形です。
4. 具体例で理解する時効判断
例:2018年1月1日に交通事故が発生し、2022年1月1日に訴訟を提起したケース。
- 修理費(物的損害) … 時効3年 → 2021年1月1日で時効完成。請求不可。
- 治療費・慰謝料(人的損害) … 時効5年 → 2023年1月1日まで請求可能。
このように、損害の種類ごとに時効期間が異なる点に注意が必要です。
一つの事故でも、修理費は時効で請求不可・慰謝料は有効、という分かれ方をします。
5. 保険金請求の時効は「3年のまま」
多くの方が誤解しがちなのが、保険会社に対する請求です。
自賠責保険・任意保険・人身傷害保険などにおける保険金請求の時効は、改正民法の影響を受けません。
- 自賠責保険金の請求 … 事故日または症状固定日から3年
- 人身傷害保険の請求 … 事故日から3年
- 搭乗者傷害保険 … 契約約款により2〜3年が多い
「人的損害=5年」と誤解して放置すると、保険金請求は3年で失効してしまう恐れがあります。
保険と民法の時効は別物として捉えましょう。
6. 死亡・後遺障害に関する時効
生命・身体に関する損害でも、起算点が異なるケースがあります。
| 損害の種類 | 時効期間 | 起算点 |
|---|---|---|
| 死亡による損害 | 5年 | 死亡日(損害を知った時) |
| 後遺障害による損害 | 5年 | 症状固定日(治療終了日) |
| 物損(車・家屋など) | 3年 | 事故発生日 |
「事故=時効のスタート」ではなく、損害を具体的に知った日からカウントされます。
入院や後遺障害の確定が遅れた場合は、その分だけ時効も後ろ倒しになります。
7. 実務での落とし穴|時効の「中断」「停止」
時効期間が経過していても、一定の行為によりリセット(中断)や停止が可能です。
- 内容証明郵便などによる請求通知 → 6か月間の効力
- 裁判上の請求(調停・訴訟) → 完全に中断し、判決確定後に再スタート
- 加害者の一部支払い・謝罪 → 承認行為として中断
「まだ交渉中だから大丈夫」と思っている間に時効が完成することもあります。
書面記録を残すことが、将来の証拠になります。
8. 時効トラブルを防ぐ3つの行動
- 事故日・症状固定日を記録し、スマホメモやカレンダーで管理
- 保険会社との連絡履歴(日時・担当者・要点)を残す
- 迷ったら弁護士相談で現状を確認(無料相談も活用)